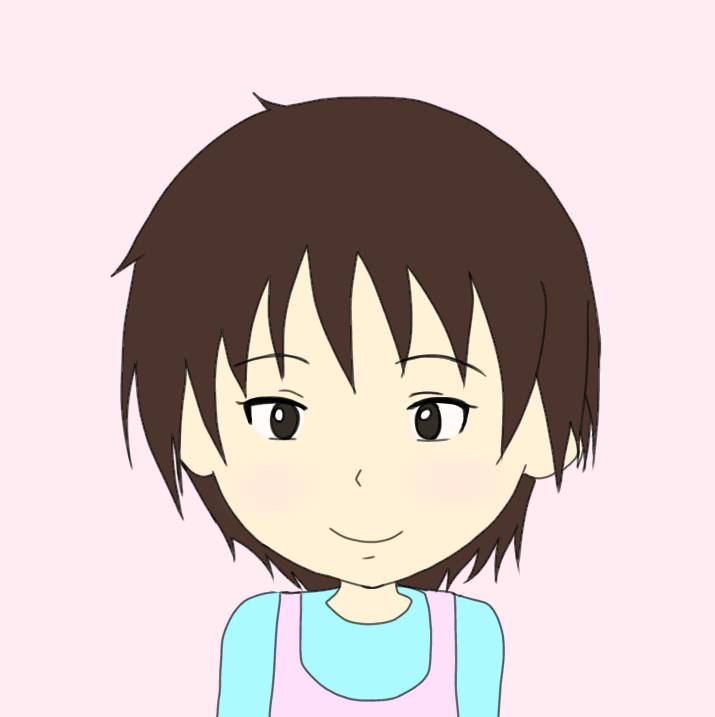経済的に余裕があるわけじゃないけれど、「少しでも厳しい環境にいる人たちを支援したい。」
そう考えている方は結構多いのではないでしょうか。
ただあなたの寄付したお金が、間違いなく困っている人たちに届いているのかどうか。
これって結構不安だったりする点ではないでしょうか。
そこでこの記事では【信頼できる寄付先の見分け方】について、私(管理人)の実体験をふまえてご紹介していきます。
目次
寄付先はどこがいいかを決める前に
 ひとくちに寄付といっても、かなり幅広いジャンルがあります。
ひとくちに寄付といっても、かなり幅広いジャンルがあります。
あなたが「支援したい!」と思っているのは、以下のどれに当てはまりますか?
・地域の身近なところ
・日本国内の困っているところ
・世界の遠く離れたところ
それでは順番に見ていきましょう。
地域の身近なところへの寄付
 「地域の身近な寄付先」には、
「地域の身近な寄付先」には、
・障害者施設
・児童養護施設
・自分が以前にお世話になった病院
などがあります。
みずから寄付を申し出れば、ほとんどの場合は感謝して受け取ってくれるでしょう。
日本国内の困っているところへの寄付

次に「日本国内の困っている場所」ですと、やはりその年の被災地が挙げられます。
日本は国単位で見ても、とても災害が多い国。
毎年、次から次へと地震・台風・大雨・洪水・土砂崩れなどが起きます。
意外と物よりも現金のほうが、様々な用途に使えるので喜ばれるようです。
また直近の被災地への寄付は多く集まりそうですが、災害から数年経過した場所は意外と忘れられてしまいます。
ですのであえて、被災から数年たってしまった被災地への寄付にしぼってみるのもいいかもしれませんね。
世界の遠く離れたところへの寄付
 視野を世界にまで広げていくと、支援が必要な人の数は膨大になっていきます。
視野を世界にまで広げていくと、支援が必要な人の数は膨大になっていきます。
個人が出来ることの小ささに、無力感にさいなまれ、結局何も出来ていないという方も多いようです。
以前の私もそうでした。
でも今や世界はインターネットでつながって、とてもコンパクトになっています。
支援するスピードもどんどん上がってきているので、決して「焼け石に水」ではありません。
そして意外なことに気がつきます。
それは困っている人たちと「自分の豊かさ」を分かち合うと、「こちらもたくさんの幸せをもらえる」ということ。
こればかりは口で表現すればするほど、安っぽくなってしまうのでぜひ体感していただきたいと思います。
信頼できる寄付先の選び方

何事においても100%大丈夫ということは存在しません。
ですので、残念ながら「寄付してはいけない団体」も存在します。
日本のNPO団体の多くが、真面目に団体運営をしています。
しかし、ごく一部の団体による不祥事や犯罪のせいで、「NPO団体=怪しい」と感じる人が少なくありません。
ただここで、しっかり見極めるポイントをおさえておくことで、ほとんどの怪しい団体を回避できます。
信頼できる寄付先かどうかを見分けるポイントは以下の通り。
❶団体の代表・職員の名前や顔が出ているか
❷団体の公式サイトは更新されているか
❸財務情報を公開しているか
❹有名企業や財団からの支援があるか
などがあげられます。
ただこれらを調べるのがちょっと面倒だという方もいるでしょう。
そしてさらにもっと間違いのない団体がいいという方は、「認定NPO法人」を選ぶのがおすすめです。
日本に約5万団体もあるNPO法人のうち、認定NPO法人はわずか2%ほど。
認定NPO法人になるには、所轄庁が定める多くの要件をクリアする必要がありハードルが高いです。
しかも更新制なので、怪しいことをしていればすぐに認定を取り消されます。
ですので、まずは「認定NPO法人」に絞って選ぶのが安心できる選択肢となります。
寄付はどこがいい? 私の体験談をご紹介!

私(管理人)は過去に、いろいろな団体へ単発的に寄付したことがあります。
決して悪くないはないのですが、いまひとつ役に立ててるのかどうかの実感がありませんでした。
実感を求めること自体、間違いだという意見もあるかもしれません。
でも自分の寄付が役立っているという実感は、私は「あるに越したことはない」と感じています。
なぜなら、私が現在おこなっている寄付を続ける意欲につながっているから。
それを強く感じさせてくれたのが、「チャイルドスポンサーシップ」という寄付でした。
厳しい環境にいる海外の子ども1人と、手紙や写真のやりとりを継続できる寄付です。
つまり毎回その子のことを思い浮かべながら支援できるので、サポート出来ている実感がずっと続きます。
さらにちょっとハードルは高いですが、その子が住んでいるところへ現地訪問することも!
自分の支援した効果が実際に見れて、しかも本人や家族に会えるので、それが夢になっている支援者も多いです。
 ➤➤➤【1人の子どもと1対1の支援プログラム】
➤➤➤【1人の子どもと1対1の支援プログラム】
※寄付金控除が適用されるので寄付額の約4割ほどが戻ってきます。
寄付はどこがいいかを私が考え始めた理由

それでは次に、私(管理人)が寄付をし始めたキッカケについて聞いていただければ幸いです。
我が家では、妻が「てんかん」と「発達障害」を持っており、お金の管理がかなり苦手です。
そういうこともあって、夫である私が「お金の管理」をしています。
寄付はもちろんいいことだとは思います。
しかし「家族のお金」でもある以上、しっかり話し合っておかないと、けっこう揉める原因になります。
家族からすれば、よくわからない団体に「家族の大切なお金を。。。」と思うこともあるはずだからです。
どんな寄付でも、家計が苦しくなった時には辞めることが可能です。
再開するのも簡単なので、それほど罪悪感を持つこともありません。
その事をきちんと伝えて、家族の了解を得てから寄付を始めるのがいいと思います。
また私自身、40歳を過ぎてから「残りの人生」を意識するようになりました。
私の親族の寿命は短く、70歳まで生きた人がいないほど。。。
去年も親の兄弟である叔父が2人、60代前半で年金をもらわないまま病気で亡くなりました。
65歳と63歳でした。
私の年齢から引き算すると、あと20年ほどしかありません。
40年間の人生で、他人が驚くような特別すごい事は何も出来ませんでした。。。
それでも一応安定した仕事につけて、家庭を持つこともできました。
19歳の時に「引きこもり」をしていた自分としては、充分に幸せだと言えます。

なので、せめてここからはもう少し「他の人のために行動したい」と思い始めました。
うちの子どもたちを責めるわけではないのですが、学校に行くことに疑問が多いようで文句がかなり多いです。(笑)
また毎日食べることに困ったことがないせいか、面倒くさそうに超早食いで終わらせます。
でも「子どもは親をうつす鏡」。
このような振る舞いを、きっと自分もやっていたのだろうと思うのです。
なぜ私はそんな態度をとっていたのか。
おそらくそれは「世界を知らなかったから」だと思います。
昔、テレビや学校で見せられた「世界の戦争や貧困の映像」に、ぜんぜんピンとこなかったことを思い出します。

それはたぶん、「本当にリアルでひどい映像」はカットされていたためです。
たしかに子どもによっては、リアルな映像で悪影響が出てしまう場合もあるでしょうから、仕方のないことかもしれません。
でももう少しインパクトのある映像だったら、なんとなく「学校に行きたくない」だの、「今日のご飯が気に入らない」など言えなかっただろうなと。
ただ何はともあれ、自分はまだ生きています。
手取り20万円の49歳サラリーマンでも出来る事があるはず。
毎年必ず1度は、貯金をはたいて「アジアの国」を旅することにしています。
観光地を周るだけでは浅い旅で終わってしまうので、現地のことを深く学べる「スタディツアー」に参加しています。
うちの子どもの言動を否定する前に、親である自分がもっと学んでいかなければと感じています。
ただ現地に行けないときも、常に海外の子どもたちの存在を意識していたい。
そんな取り組みの1つとして【チャイルドスポンサーシップ】に参加し始めました。
寄付金控除について
寄付金控除は、寄付をした人の税金を安くしてくれる制度。
1年間の寄付した金額に応じて、税金の軽減額が変わります。
寄付金額の25~40%が戻ってきます。
日本は世界的に見て、寄付する人も金額も少ないです。
そのため寄付を促進するために、この優遇措置がもうけられました。
確定申告をする必要があるので難しく感じるかもしれません。
でも寄付金控除だけの確定申告ならかなり簡単。
確定申告と縁がないサラリーマンの私でも、ちょっとネットで見たら簡単に出来ました。
ただ寄付金控除を受けられるのは、おもに国が認めた「認定NPO法人」への寄付。
認定NPO法人以外では、以下のような団体が寄付金控除を受けられます。
日本赤十字社(公益社団法人)
国境なき医師団(公益財団法人)
日本ユニセフ協会(公益財団法人)
あしなが育英会(公益財団法人)
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(公益社団法人)
あしなが育英会(公益財団法人)
母子寡婦福祉会(社会福祉法人)
お住まいの自治体(災害義援金など)
ふるさと納税(各自治体)
まとめ 寄付はどこがいい?
どんなに大手の有名な団体であっても、他人のお金を扱っていると魔が差す人が出てくる可能性はあります。
ただ、疑ってばかりでは一生寄付することができません。
ですので、自分なりに寄付先を調べて「納得しておくこと」が大切だと思います。
私は数年前に「寄付はどこがいいか?」を考え始め、たまたま信頼できそうで、かつ面白そうな団体を見つけました。
それがワールドビジョジャパンの「チャイルドスポンサーシップ」でした。
厳しい環境にいる海外の子ども1人と、手紙や写真のやりとりを継続できる寄付です。
どんどん成長する子どもの写真を見るたびに支援できている実感が湧きます。
興味のある方はぜひチェックしてみてください。
 ➤➤➤【1人の子どもと1対1の支援プログラム】
➤➤➤【1人の子どもと1対1の支援プログラム】